コラム
Column対面し続けること
先の見えない事態に世界中が混乱していた。
舞台ももちろん例外ではなく、新型コロナウィルス感染症の影響により、あっという間にこれまでの常識が変わっていった。私自身も大きな公演が2年に渡り中止に追い込まれることとなり、どうすることもできない苦しい時間が続いた。
これまで当たり前のように観客の前で上演されてきた舞台が、無観客上演、映像配信、様々なものに形を変え必死で生き残ろうとしていた。
その中で私は、そのような新しい道に踏み込めずにいた。

2021年度は、自身の活動に対する考え方、取り組み方を問い直す一年であったと思う。
インターネットやSNSがどんどん発達し、速度はますます速く、より簡単に情報を得ることができるようになった今、世の中の状況がそれにさらに拍車をかけることになった。私たちはある意味とても速度の遅い「舞台芸術」をやってきたわけである。その価値は何なのか、自分たちがやってきたことを考え直す時間を与えられたと思う。
観客は、車や電車や自転車に乗り、または歩いて、劇場にやってくる。そして1時間や2時間という決して短くはない時間を拘束され、また同じように時間をかけ、それぞれの家に帰る。
私はこの工程の中に、舞台芸術の意味があると思っている。嫌なら消せる、面倒くさければ早送りできるわけではない「現実」と地続きに、たった今その目の前で、舞台に立つ人、起こることを目撃し、それぞれの生きる世界に持ち帰る。舞台は観客に手渡されてから観客の中で増幅される思考の時間までが作品であるべきだと思う。
逆に舞台に立つものたちは、観客の反応を引き受ける。観客の前に立たされ、対面し、初めて舞台作品が完成する。
その面倒くさくもある速度の遅さを失ってはいけないと思った。
そんな状況下で、2021年度、私は二人の作家と共に作品を作ることになる。演出家の飴屋法水と、ダンサー・振付家の山田せつ子である。
彼らは私より遥かに長く生きていて、遥かに長い舞台キャリアのある2人である。彼らは色んな時代を舞台活動と共に生き抜いてきた。
そんな人たちと、今、この時代に、私たちが出来ることはなんだろうか、と顔を突き合わせる。速度がどんどん増し、便利になってきた現代に生まれた私が彼らに向かい合うとはどういうことか。
生きてきた時代、それぞれの思考を共有する。簡単には理解し合えないこともあるし、足がすくみ立ち止まることもあった。自分の経験の浅さにガッカリする。ただ、時代を超えて、互いの作家性を通して初めて知ることができることもある。初めて見る世界がある。
彼らの中には長い「時間」があった。「今」は、過去の蓄積であり得るものなのだ、と、感じた。
「今」になるために長い長い時間がかかっている。今だけがここにパッと存在しているわけではない。
「年寄りの思い出話にしたくないの」と、山田せつ子さんが私に言った。その時私は、山田せつ子と共有した時間で得たものを、しっかり私のこととして提示することが重要だと思った。そしてそれを観客に思い出話としてではなく、現在のこととして伝える。

それは、私がこれまで自身の作品で関わってきた薬物依存リハビリ施設の利用者たち、認知症のおじいさん、在日コリアンの人々、子供たちなど、たくさんの他者の中に自分を動かす何かを感じた時と同じである。
違う時間を生きてきた人の中に自分を発見する。
飴屋法水さんは、現実とフィクションの間を彷徨っていた。微妙なその狭間で、悩んで考え込む。舞台を作りながら、ずっと現実と向かい合ってきた。現実とは「社会」であり「今」である。私にとってのその境界はどこであるか。ダンサーや俳優ではない一般の人と多く作品を作ってきた私は、改めてその危険性や、暴力性を突きつけられる。ただ、その境界は舞台が持つ可能性でもある。
彼らとの共同制作の時間は、まさに速度の遅い舞台芸術のように、自分の思考が増幅していく、今の状況を長い歴史の一部分として俯瞰できる時間だった。

ある少女が作品を見にきてくれた。「何故かわからないけど、涙が出た。なんで涙が出たのか言葉にしたいんだけど、説明できない。」と伝えてくれた。
ほんの十数年の彼女の歴史の中にある何かが作品とフィットした瞬間である。時間を掛けて、遠い未来で、その涙のことを思い出してくれたらいいなと思う。
すぐにはわからないかもしれない、すぐに結果が出るものでもない、ただゆっくりと、観客の日常に静かに添える時間を提供すること。次の世代にバトンタッチされていく「今」を捉え続けていくこと。現実の世界との境界線のギリギリをフィクションとして立ち上げること。
それが私にとっての舞台であると改めて感じた。これは、生でしかできないことである。人と人との関係の中からしか立ち上がらないものである。
これからも不安な日々は続くけれども、それでも今を生きていきましょうと、そう感じられる作品を作りたいと思っている。
また、海外との行き来が自由になる日が来た時に、生きてきた場所の違う人々、違うルールの元で生きてきた人々の前で、自分の作品がどのように受け止められるのか、私はどのように対面することができるのか、チャレンジしたいと思う。
**********
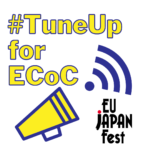
*プッシュ型支援プロジェクト#TuneUpforECoC 支援アーティスト*
https://www.eu-japanfest.org/tuneupforecoc/
(*2022年1月にご執筆いただきました)








