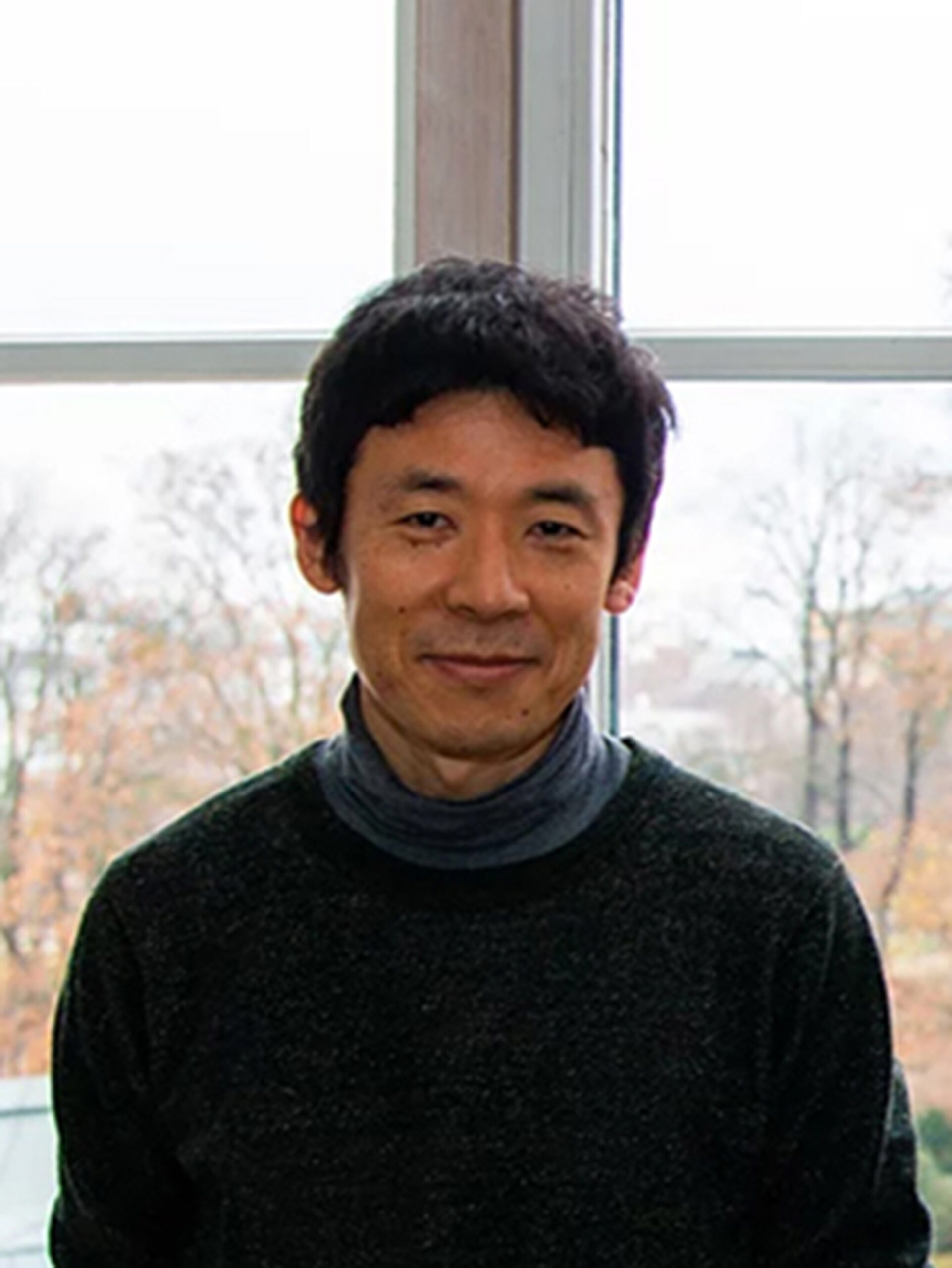コラム
Column鏡をみつめる知性
Mirrored Journey 2021-2022
“Mirrored Journey”プロジェクトは、私とヴィジュアル・アーティストのヴィオレッタ・イヴァノヴァとの協働プロジェクトとしてコロナ禍の2021年に始まりました。小さな丸い鏡に、自分自身やコミュニティにとって大切な場所や物語、考えなどを鏡に映し、それをスマートフォンで撮影し、その写真と撮影の背景となった考えをインスタグラムとホームページで公開しました。我々が旅をできない代わりに鏡が旅をすることで、様々な経験を共有したのです。鏡の送付先は私とヴィオレッタの友人を起点とした個人的な繋がりではじまりましたが、鏡は友人を介してさらにその友人に送られ、そしてさらにその友人に送られ、というオープン・エンドな広がりとなり、2021年から22年にかけて35カ国から66名の参加者がありました。このプロジェクトについては、2022年レポートをご覧ください。
Mirrored Journey 2024
コロナ禍からアフターコロナへの状況変化において“Mirrored Journey 2021-2022”の新たな展開を図ろうとしたのが本プロジェクトです。本プロジェクトの発案は、単なる継続ではなく、コロナ禍を経て、新たな連帯のあり方を探る必要があるという問題意識から発案されました。
コロナ禍が収束し自由に旅ができるようになってから気が付いたのは、我々が狭い世界の中で暮らしているということです。東京からヨーロッパ、アメリカ等に移動し、あたかも国際的に暮らしているように思いがちですが、実はどこへ行っても自分と似たような人たちとしか会っていないのです。現代社会で問題となっている様々な社会的分断は、このような自分と似た人達との交流ばかりで、それ以外の人達との交流が行われないことによって引き起こされているように思います。そこで「自分と違う世界に住む人」や「自分と考えが違う人」との交流を図るには、「鏡の旅」という手法が有効ではないかと考えました。

本プロジェクトでは、ポストコロナの状況を反映し、日本とオーストリアの文化団体と協働することで参加者の多様化を図りました。 “Mirrored Journey 2021-2022”が我々の友人を起点に行われたのとは異なり、様々な人々との連帯を目指したのです。そして、その成果を展示したのがオーストリア文化フォーラム東京で開催した展覧会です。展示台は上下二枚の板によって構成され、上面の写真を下面の鏡384枚をとおして見るという展示構成となっています。鏡をとおしてみた世界(写真)を再び鏡をとおしてみるという方法によって、表面的で一元的な見かたとは異なる経験を提供したいと考えました。
烏賊(イカ)と鏡
展覧会関連イベントとしてキュレーターの天野太郎氏とトークイベントを行いました。天野氏との対談では、烏賊(イカ)の鏡による実験に話がおよびました。
イカは群れをつくるため社会性があると言われています。本当にイカに社会性がある否かを確かめる実験に鏡が用いられました。鏡に映った自分を自分であると認識できるか否かを確かめる鏡像自己認識実験です。社会を築くには、まず自分という概念をもつことが重要であり、それによりその対概念である他者という概念も形成されるというわけです。多くの動物は鏡に無関心ですが、イカは異なり実際に鏡に映る自分と仲間のイカを区別して認識し、鏡像自己認識をもつことがわかっています。イカは社会を築くための「知性」をもっているのです。

動物的感覚
これまで人間の感覚は、アリストテレス以来の西洋哲学の文脈において、視覚と触覚の対比によって理解されてきました。視覚は知性と結びつくため視覚が最も優れた感覚とされる一方で、触覚は動物も所持する最も劣る感覚として理解されてきました。この視覚と触覚の関係を反転し、触覚の重要性を唱えたのが20世紀初頭に活躍した哲学者ヴァルター・ベンヤミンです。ベンヤミンによる変革は、20世紀初頭に本格的に出現した映画という新しいメディアによって導かれます。ベンヤミンによれば、映画は画面をみた瞬間に次の画面に移り変わるため視覚では捉えられないとして、動物的な感覚である触覚の重要性を指摘しました。つまり、人間が生まれながらにして所持する触覚こそ本当の知性であるとして価値を見出したのです。
動物的知性
今日においてArtificial Intelligence(AI)、つまり人工知能の有用性は益々大きくなり、今後も我々の社会に活用されていくことになるでしょう。それにより我々は人間の知性とは何か、が問われる事態に直面しているように思います。AIとは人間の知性をデータとして集積し、アルゴリズムによってコンピューター処理することで実行される技術です。たしかにAIの有用性は、記憶や処理速度が人間よりもコンピューターが優れていることから導かれています。しかしAIが扱う人間の知性とは、所詮、人間が生まれた後に学習することによって身に着けた知性に過ぎません。そのため、ベンヤミンがみいだした人間が生まれながらに所持する動物的な知性の重要性は、AIの出現によって益々高まるでしょう。今回の展覧会で鏡を見つめる我々には、そのようなイカも所持する動物的で本能的な知性が問われていたように思います。そう、展覧会場で「現代美術はよくわからない」と呟いたあなた自身の本当の知性が試されていたのです。
謝辞:今回の事業はEU・ジャパンフェスト日本委員会の他に、一般社団法人東京倶楽部、オーバーエスターライヒ州、オーストリア文化フォーラムから助成をいただきました。またアートセンター・オンゴーイング(東京)、コスモス・シアター(ウィーン)、KUK pro mente(リンツ)、アトリエ・ヴェルス(ヴェルス)、滝沢広さん、株式会社wood凪の皆様にご協力いただきました。感謝申し上げます。