コラム
Columnわたしのからだはわたしのものか?
2021年12⽉に愛知県芸術劇場で世界初演を迎えた三作品全てに通底していたのは、「わたしのからだはわたしのものか?」という現代における⾝体の存在意義をめぐる疑問であった。
少⼦⾼齢化が進み、AI などのテクノロジーが⾶躍的に進化し続ける現代。そこに降りかかったコロナ禍は我々の⽣活を根底から⼤きく転換することとなった。変⾰の時を迎えている現代社会において、我々ダンサーが表現の拠り所とする⾝体はいかなる価値を持つのだろうか。
科学技術分野において内閣府が主導している政策の⼀つに、「ムーンショット型研究開発制度」というものがある。内閣府のウェブサイトによれば、「超⾼齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、⼈々を魅了する野⼼的な⽬標(ムーンショット⽬標)を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進するもの」だそうだ。(https://www.jst.go.jp/moonshot/jigyou.html)
紹介されている九つのムーンショット⽬標のうちの⼀番⽬には、「2050年までに、⼈が⾝体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」とある。その中の具体的な例の⼀つに「2030年までに、1 つのタスクに対して、1 ⼈で10 体以上のアバターを、アバター1体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運⽤等に必要な基盤を構築する」というものがある。あと8年⾜らずの間に、我々をこの⾝体から解き放つことを⽬指そうというものだ。(https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html)
これはもちろん、政策名にムーンショット(=⽉にロケットを打ち上げること)」とあるように、あくまでも「実現困難だけれどもそうなったらすごいよね」という性質のものだが、まるで私たちのこの⾝体がなくてもよいものであるかのような⽅向を、社会が向いてしまっていることに、私は⾝体表現者として⼤きな危機感を感じるのである。
私はダンサーとしてのキャリアを経て、振付家として活動している。ダンサーになるための専⾨的な⾝体訓練を受け、この⾝ひとつで世界を渡り歩いてきた。⾝体は私にとって、私の⼈格を形成する私固有のものであり、表現媒体としても「なくてはならないもの」である。しかし、想像していたよりも多くの⼈にとってはそうではないのかもしれない。⾝体の存在意義は、現代において⼤きく揺らいでいると⾔えるのではないだろうか。

「⾝体の不在」が跋扈する現代社会における、ダンサーの苦悩と悦びを、『never thought it would』と『Proxy』は象徴しているのかもしれない。この「⾝体の不在」というテーマは、⾝体の存在意義が揺らいでいる現代であるからこそ、私のこれからの振付家⼈⽣において引き続き探求していきたい。私は、⽣⾝の⾝体を絶対に⼿放したくない。そこにしか産まれ得ない価値を追求していきたいと強く感じている。
また、⾃分の⾝体が不要なのであれば、他者のそれはどうだろうか。
私は振付家である。それはつまり他者の⾝体を媒体とした振付という⾮対称的な⾏為によって表現活動をする⼈間であることを意味する。この振付家とダンサーという⾮対称的な関係性と、⾃分の作品が他者の⾝体によって成⽴しているという事実に、我々振付家は常に意識的でなければいけない。クリエーション中のスタジオにおいて振付家は常に、(それが意識的であれ無意識的であれ)他者の⾝体の⼿綱を握ってしまっている存在なのだ。これはダンス作りの現場に限らず様々な組織の中で意識されるべき問題である。『When will we ever learn?』では、そのような⾮対称的な⼈間関係が蜘蛛の巣のように張り巡らされて形作られている現代社会におけるコミュニケーションのあり様をダンスとして表出させることに取り組んだ。

真に対照的な関係性などというものがこの世に存在し得ないという現実は⾃明である。そして同時に⼈対⼈、組織対組織、⼈対組織の関係性のあり⽅とコミュニケーション⽅法は、これまでとは比にならないスピードで変化し続けている。そんな現代社会において、振付家によって強いられた振付を踊るだけの機械であるかのようにダンサーを扱い消費していく前時代的なクリエーションによって産まれた作品を、果たして現代的(=コンテンポラリー)と呼んでも良いのだろうか。
ダンサーとの関係性だけでなく、様々な専⾨性を持った他者の存在がダンス作りには必要不可⽋である。そうしたスタッフたちも含めた、作品制作に関わる誰しもがその作品との関わりにおいて「わたしのからだはわたしのもの」と⾔える、真にコンテンポラリーな作品とクリエーション環境を、私は⽬指していきたい。現代的なテーマを扱うだけでなく、その作品を⽣み出すプロセスにおける現代性を追求することこそ、今の⽇本に⽋けているものなのではないだろうか。
作品上演環境についても、同じことが⾔える。⽇本国内における再演をめぐる環境は、私が帰国してからのこの数年を⾒ても芳しくない。どれだけ時間と労⼒をかけても、数回上演したらそれで終わりである。
作品を作っては捨てを繰り返し消費していく舞台業界の現状は明らかに⾮⽣産的であり、近年活発になっているサステナビリティに関する議論に逆⾏するものだ。再演への取り組みは、さまざまな観点からもっと⽀持され、⽀援されるべきであると私は考えている。

また、少なくともこれまでに私が作ってきた作品においては、初演の段階で完成といえる形になっていたことは⼀度としてない。上演を通じて初めてわかることが多々あり、修正が必要になってくる。様々な⼟地や⽂化圏での上演を通じて、多種多様な観客の⽬に晒すことで作品を磨き上げていくプロセスが、本来必要不可⽋なのである。しかし、⽇本では初演する段階でそれなりのクオリティで作品が完成されていることが求められる。⼀つの作品を醸成していくよりも、たくさんの作品を次々に産み出すことに重きを置いた新作主義とも⾔える現状を、果たして現代的(=コンテンポラリー)と呼んで良いのだろうか。
⾃分の⾝体を消費しない。他者の⾝体を消費しない。そして、作品を消費しない。そのためにも、そこにあるものの価値を認め、⼤切にする「もったいない精神」が今こそ必要なのではないだろうか。「もったいない(勿体ない)」という⾔葉は、仏教⽤語に由来する⾔葉だそうだ。「勿体ない」はもともと「物体ない」と書き、「物の本体はない」ということを意味する。すべての事物は繋がりあって成り⽴っており、単独で存在するものはこの世にないということだ。私たち⾃⾝もダンス作品も、様々な要素によって成り⽴っており、⾝体はその⼀部である。そしてその⾝体も常に新陳代謝を繰り返す流動的なものであり、いつかは消えて無くなってしまう、いわば本体のないものである。すべての事物が繋がっているのに、物を粗雑に扱い物の持つ本来の価値を無くしてしまうことに対して我々はもったいないという⾔葉を使う。
それは⾃⾝の⾝体に対しても、他者に対しても、作品に対しても同じことが⾔えるはずである。
現代を⽣きる私たちの儚い⾝体の記憶を、⾝体によって記録し、⾝体によって作品化し、他の⾝体(=他者)と共有する営みのことを、私たちはコンテンポラリーダンスと呼んでいるのではないだろうか。

**********
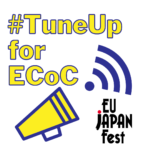
プッシュ型支援プロジェクト#TuneUpforECoC:支援アーティスト
https://www.eu-japanfest.org/tuneupforecoc/








